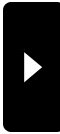この疲れ、体のカチカチ、早く何とかしたい。元気に復活したい。という方、
腰痛、肩こり、頭痛でお悩みの方、
私の主人がお役に立てるかもしれません。
よかったらお試しください。
お疲れお母さん、お子様と一緒にどうぞ。
疲労回復、痛みの軽減、お身体のケア・
メンテナンス、心身のリフレッシュに!
豊橋 池田整体 090-9930-4310
2014年07月31日
モクヨウのうなぎのはずが、、、
おはようございます
昨晩、仕事を終えた主人、夕飯をすませ、長女と長男を連れ豊川へ。
「明日の晩はモクヨウのうなぎにするぞ!ニヤリ」と言い残し、嬉しげに出発。
暗闇の中、糸を3本たらし、竿を竿置きに立てかけ、あたりがあるのを3人並んでじっと待っていたそう。
チョン、チョン、竿の先の蛍光マーカーがかすかに動く。
「お父さん、来てるよ。来てるよ。うなぎかなぁ?」
「おぉ。多分ね。もう少し待つか(餌を飲み込むまで)。」
その時、竿がひっくり返って、ズルズルと水の中に引き込まれていったそうです。
とにかくアッという間の出来事。
なにも考えずに大事な竿を追い、水の中へ走りこむ主人。
陸から「お父さん、行っちゃだめ~」と半泣きで叫ぶ娘。
ズボンのポケットに携帯電話と車の鍵が入っていることに気づき、泣く泣く竿(もちろんリール付)を諦め引き返したそうです。
「エイかシーバスの仕業に違いない。」と朝になっても悔しさを隠しきれない主人。
携帯と鍵がポケットに入っていなかったら、彼はきっとチャレンジしたに違いない。
ひざ上までびしょびしょのズボンと運動靴をお風呂場で流しながら、新聞の見出しが想像できちゃって、怖い怖い。
「夜釣りの男性(39歳)、竿を追いかけ豊川で流される」
「アッパレ!小2と年中の姉弟、冷静な判断で父救う」
皆様、夏休み中の川の事故。本当に誰にでも起こり得るようです。
くれぐれも気をつけましょう。

昨晩、仕事を終えた主人、夕飯をすませ、長女と長男を連れ豊川へ。
「明日の晩はモクヨウのうなぎにするぞ!ニヤリ」と言い残し、嬉しげに出発。
暗闇の中、糸を3本たらし、竿を竿置きに立てかけ、あたりがあるのを3人並んでじっと待っていたそう。
チョン、チョン、竿の先の蛍光マーカーがかすかに動く。
「お父さん、来てるよ。来てるよ。うなぎかなぁ?」
「おぉ。多分ね。もう少し待つか(餌を飲み込むまで)。」
その時、竿がひっくり返って、ズルズルと水の中に引き込まれていったそうです。
とにかくアッという間の出来事。
なにも考えずに大事な竿を追い、水の中へ走りこむ主人。
陸から「お父さん、行っちゃだめ~」と半泣きで叫ぶ娘。
ズボンのポケットに携帯電話と車の鍵が入っていることに気づき、泣く泣く竿(もちろんリール付)を諦め引き返したそうです。
「エイかシーバスの仕業に違いない。」と朝になっても悔しさを隠しきれない主人。
携帯と鍵がポケットに入っていなかったら、彼はきっとチャレンジしたに違いない。
ひざ上までびしょびしょのズボンと運動靴をお風呂場で流しながら、新聞の見出しが想像できちゃって、怖い怖い。
「夜釣りの男性(39歳)、竿を追いかけ豊川で流される」
「アッパレ!小2と年中の姉弟、冷静な判断で父救う」
皆様、夏休み中の川の事故。本当に誰にでも起こり得るようです。
くれぐれも気をつけましょう。
2014年07月30日
地域医療を守るために
こんばんは
今日は小2の娘と年中の息子と中消防署で「救急医療講座」を受けてきました。
小学生とその親を対象にした講座で、子供たちは防火服を着せてもらったり、消防車や救急車にのせてもらったり。


署内の消防指令センターの見学では、実際に参加した小学生が携帯から119番をして、センター内で隊員達がどのような動きをするかを見せていただけました。
教えていただいたことを記録もかねて書いてみます。
中消防署の指令センターでは、東三河の5つの市(豊橋・田原・蒲郡・豊川・新城)の全ての119番の電話を受けつけ、場所の確認、必要な救助の内容を把握してから、現場にもっとも近くにいる消防車や救急車に出動指令を出しているそう。
119番する際にもっとも大事なことは救助を必要としている場所を正確に伝えることだそうです。出来れば固定電話からの通報が望ましい。屋外にいる場合で、携帯電話で通報する場合は、ピンポイントでの場所の把握が難しいので、住所や、目標となる建物を確認してから電話して欲しいとのことでした。
親子での施設見学の後、保護者を対象に救急医療講座。
地域医療の現状とその医療体制を守るために私達が協力できること(しなければならないこと)について講義がありました。
私達がひとくくりに病院と表現する医療施設は、実際は3つの段階別で役割分担をしているそう。
〇〇医院、〇〇クリニックと呼ばれる診療所は、第1次救急医療と呼ばれ、市民のかかりつけ医になる存在。比較的軽症な患者を扱います。
次に病院と名のつく医療施設(豊橋には現在8つ)で、第2次救急医療機関と呼ばれ、入院治療が必要な重症患者を扱います。
最後の砦が豊橋市民病院の属する第3次救急医療機関。重篤な患者を扱います。
この医療機関の役割分担がきちんと出来ていないのが現状。市民病院や、第2次のグループに属する病院をかかりつけ医のように利用する患者が多く、肝心の重篤な患者の診療の妨げになっているそう。
また、救急車利用者の6割近くが軽症者というデータもあり、同じように、重篤な患者の命を救う妨げになってしまっているという話もありました。
東三河の地域医療は他の地域のそれに比べて恵まれているといえるそう。
ただし、こういう状況が続くと、第2次、第3次救急医療機関の医師やスタッフの負担が増え、医師不足が深刻化し、診療科数を減らしたり、診療時間を制限したりと、制度として成り立たない状態になってしまいかねないそうです。
まだ制度が成り立っている今のうちに、市民ひとりひとりが地域の医療制度の役割分担について理解して、適切な利用の仕方をして地域医療を守っていきましょう。との事でした

今日は小2の娘と年中の息子と中消防署で「救急医療講座」を受けてきました。
小学生とその親を対象にした講座で、子供たちは防火服を着せてもらったり、消防車や救急車にのせてもらったり。
署内の消防指令センターの見学では、実際に参加した小学生が携帯から119番をして、センター内で隊員達がどのような動きをするかを見せていただけました。
教えていただいたことを記録もかねて書いてみます。
中消防署の指令センターでは、東三河の5つの市(豊橋・田原・蒲郡・豊川・新城)の全ての119番の電話を受けつけ、場所の確認、必要な救助の内容を把握してから、現場にもっとも近くにいる消防車や救急車に出動指令を出しているそう。
119番する際にもっとも大事なことは救助を必要としている場所を正確に伝えることだそうです。出来れば固定電話からの通報が望ましい。屋外にいる場合で、携帯電話で通報する場合は、ピンポイントでの場所の把握が難しいので、住所や、目標となる建物を確認してから電話して欲しいとのことでした。
親子での施設見学の後、保護者を対象に救急医療講座。
地域医療の現状とその医療体制を守るために私達が協力できること(しなければならないこと)について講義がありました。
私達がひとくくりに病院と表現する医療施設は、実際は3つの段階別で役割分担をしているそう。
〇〇医院、〇〇クリニックと呼ばれる診療所は、第1次救急医療と呼ばれ、市民のかかりつけ医になる存在。比較的軽症な患者を扱います。
次に病院と名のつく医療施設(豊橋には現在8つ)で、第2次救急医療機関と呼ばれ、入院治療が必要な重症患者を扱います。
最後の砦が豊橋市民病院の属する第3次救急医療機関。重篤な患者を扱います。
この医療機関の役割分担がきちんと出来ていないのが現状。市民病院や、第2次のグループに属する病院をかかりつけ医のように利用する患者が多く、肝心の重篤な患者の診療の妨げになっているそう。
また、救急車利用者の6割近くが軽症者というデータもあり、同じように、重篤な患者の命を救う妨げになってしまっているという話もありました。
東三河の地域医療は他の地域のそれに比べて恵まれているといえるそう。
ただし、こういう状況が続くと、第2次、第3次救急医療機関の医師やスタッフの負担が増え、医師不足が深刻化し、診療科数を減らしたり、診療時間を制限したりと、制度として成り立たない状態になってしまいかねないそうです。
まだ制度が成り立っている今のうちに、市民ひとりひとりが地域の医療制度の役割分担について理解して、適切な利用の仕方をして地域医療を守っていきましょう。との事でした

2014年07月29日
年中さんの宿題
こんにちは
うちの長男は食わず嫌い王。
卵と乳製品を食べると強いアレルギー反応がでることもあり、小さいころから食べられるもの、好きなものをとにかく食べることに重点を置いてきました。
そのつけで、、、、
アレルギーとは全く関係ない野菜や果物、初めて口にする料理にほとんど手をつけない子になってしまいました。
先日、小2の姉と参加した小学校の子ども会主催のバイキングで、彼が食べたものは白米を茶碗に3杯のみ
これはまずい。完全に私の責任。
というわけで、今年の夏休みの私と彼の宿題。
『食わず嫌いを克服する!』
毎日、少しずつ頑張ってます!





うちの長男は食わず嫌い王。
卵と乳製品を食べると強いアレルギー反応がでることもあり、小さいころから食べられるもの、好きなものをとにかく食べることに重点を置いてきました。
そのつけで、、、、
アレルギーとは全く関係ない野菜や果物、初めて口にする料理にほとんど手をつけない子になってしまいました。
先日、小2の姉と参加した小学校の子ども会主催のバイキングで、彼が食べたものは白米を茶碗に3杯のみ

これはまずい。完全に私の責任。
というわけで、今年の夏休みの私と彼の宿題。
『食わず嫌いを克服する!』
毎日、少しずつ頑張ってます!